プロのあるあるレコーディング現場シナリオ①:アンプ録音の先送り(ラインのリアンプ)
例えば、ベースをレコーディングしている場面を想像してみましょう。アンプにマイクを立てようとした時、「(アンプにマイクは立てずに)後でラインをリアンプしましょう」という事になったとします。この事から間違いなく分かるのは、「今、アンプの音を固定してしまいたくない」というスタンスです。
この判断が及ぼすメリットとデメリットは一体何でしょうか?
恐らくメリットは、あとで好きなアンプや好きなマイクを選び、ゆっくり音作りしながら録ることができるという点。それと、演奏者のミスが予想される場合、単純に編集作業が楽だからという点が考えられます。
逆にデメリットとしては、リアンプが終わるまでベースの個性が定まらないという点がひとつ。またそれに伴って、その上に重ねるすべての音の方向性も、それだけ曖昧になるという事です。
製作現場の環境や音楽の性質によって、どちらが良いかは一概には言えません。しかし、いずれの場合にせよ、それぞれの結果を想定した上で最善の決断を下す必要があります。

プロのあるあるレコーディング現場シナリオ②:ギターエフェクトの後掛け
次に、ギター収録の例を見てみましょう。
レコーディング時の話で、仮に「録り音にはギターのディレイペダルは使わず、あとでプラグインでかける」事になったとして、この判断の意味を考えてみます。
まずメリットとしては、ベース時と同じく、ディレイが無い分エディットがしやすい点が挙げられます。エディット後にディレイをかければ、たとえばディレイ音をグリッドにピッタリあわせたりすることも出来るので、そういう機械的な質感を目指している場合はその点もメリットの一つと言えます。
逆にデメリットとしては、やはりディレイのキャラクターやタイミングがかっちり決まらないままレコーディングが進んでいく点です。後発の演奏者は、「とりあえずの設定」に音を重ねていくわけですから、演奏にこだわればこだわるほど、ミックス段階で土台が変わった時の「崩れ」が大きくなるわけです。
また、メリットにもデメリットにもなり得る事として特筆に価するのが、アンプを拾うマイクの後に掛けられたディレイ音には、部屋鳴りが含まれない点が挙げられます。
見落としがちな点ですが、当然ながらアンプの前に設置したエフェクトはアンプの出音に直接影響しますので、出音の一部として部屋で複雑に反射した後マイクに届きます。
一方、マイクの後にエフェクトを掛ける場合は、それがコンパクトエフェクターやプラグインであれ、エフェクトフィードバック音に部屋鳴りは含まれませんので、音の質感に明らかな違いがあります。
当たり前の事ですが、実際に音を比較する人が少ないのか、かなり軽視されている事実です。一長一短あるので、どちらが良いということはありませんが、どちらを選ぶにせよ、少なくとも違いをを知った上でどうするべきか決めたほうが良いでしょう。

プロのあるあるレコーディング現場シナリオ③:ボーカルのコンプ処理
今度は、ボーカル録りの時「コンプはマイルドな設定にしましょう」となった時を想定してみます。
メリットは、種類の違うコンプレッサーを複数台使うことで、キャラクターの違うコンプレッションを活かした音作りをする事ができる点です。また、段階的な処理をする事で、微調整が利くという事も挙げられます。
目立ったデメリットはこの場合は特にない様に思いますが、強いて言えば「マイルド」というありがちな表現が絶対性に欠けるという点です。人によればほとんど回路を通すだけの場合もあるし、5dBから10dBくらいのゲインリダクションでも「マイルド」と捕らえる人もいます。この点については、自分の中で機材や声質毎に基準を設けておくことが大切だと思います。
決断の良し悪し①:「プロらしさ」が音楽の可能性を殺すシナリオ
最終的なレコードの完成度は、こうした各段階における小さなメリットやデメリットの重なり合いによって影響を受けていくわけですが、そもそも音楽の良し悪しとは感覚的なものです。ベルトコンベアで運ばれる工業製品のように一律な製造工程で作ったとしても、人に与える感動の量までコントロールできるわけではありません。
過激な意見かも知れませんが、「良い音楽の作り方」とか「売れる音楽とは何か」という議論のほとんどは、商業的に保守的な観点からなされている場合が非常に多いものです。
当然ですが、面白い音楽を作るための方程式にのっとって作られた時点で、その音楽はまったく面白くないのです。良い音楽を作るレシピなどという幻想とは裏腹に、確実に音楽をダメにする考え方というものがあります。それは、冒険を恐れる精神です。冒険を恐れて為された決断は無難な結果以外何も生みません。
「後になっていつでも変更できるように」、「たくさん選択肢があったほうが良いから」、「今決めるのは早い」などは一見効率的でこなれたプロっぽい意見に聞こえますが、選択肢を増やしに増やし、決断を先延ばしにしたとしても、最後に欲しいのは「たった一つの個性的な音」だけです。「とりあえず可能性を10個用意してからじっくり選びたい」という選択が正しい場合ももちろんありますが、音楽はそもそも時間芸術なのだという本質を忘れてはなりません。転ばぬ先の杖を何本も用意している間に失われた瞬間の輝きは、プラグインをいくら挿した所で、もう決して戻っては来ないのです。
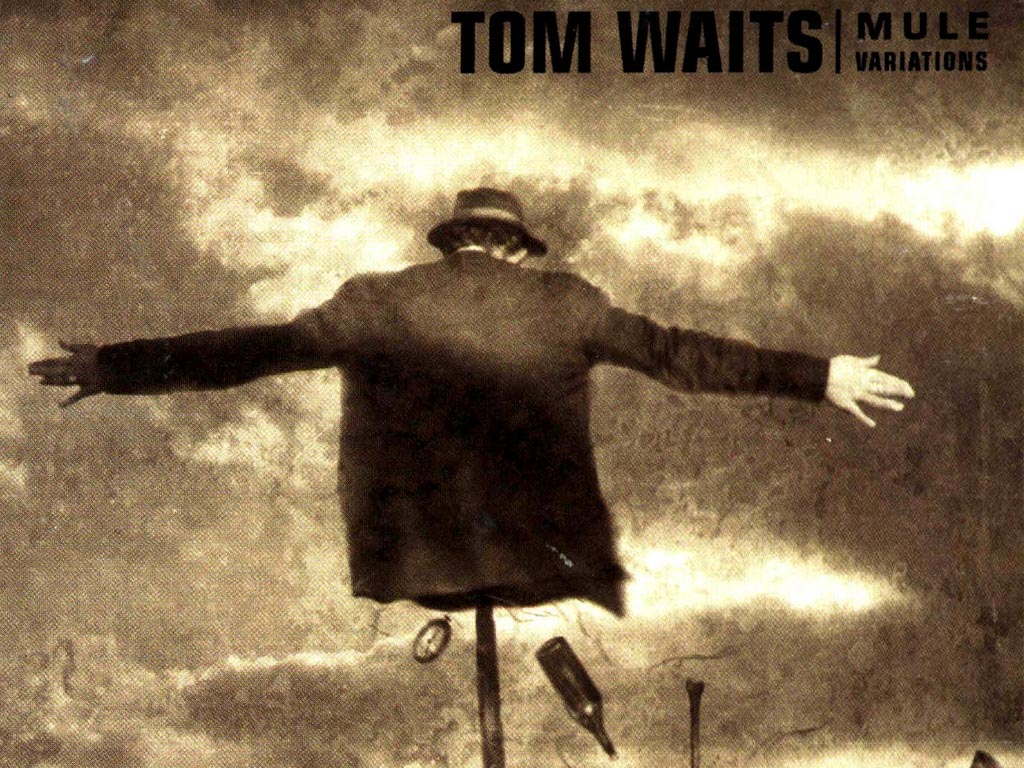
決断の良し悪し②:保守的な判断が活きるシナリオ
とはいえ、いつも十分な状況が整った環境で仕事が出来るとは限りません。気が進まないながらも、自分が思い描く「最高の選択肢」を諦めざるを得ない事も多くあります。
例えば、レコーディングの段になっても、未だ誰も目指すべき音が見えていない場合。プリプロダクションの段取りが悪かったのか、誰かの気が変わったのか、要するに準備不足な状態でレコーディングが進行しているケースがあります。こういった場合、その場で解決しそうも無く、後日の再録が難しいときは、とにかくあらゆるシナリオを想定した上で、無難な音を録らざるを得ません。
また、演奏者が技術的に未熟で、収録後多くのエディットが必要だったり、後日部分的に録りなおしになる可能性が予想される場合は、とにかく最終的な音のチグハグさを最小限に抑えるのが最優先事項となり、度重なるテイクを通していかに無個性でフラットな、エディットしやすい音を収録するかが重要になります。音楽の本質と逆行しているようですが、そもそも音の個性を考えているレベルではないという悲しむべきケースです。
他にも、機材の不調や故障、何らかの理由による収録順序の変更、場所の変更、予算的、または時間的な都合や突発的な第三者の介入などなど、レコーディングには常にアクシデントが付きまとう物です。
そんな時には、悔しさはあれどグッと堪え、一歩引いて無難な守りに入るという決断を下す姿勢も、プロに必要な立派な資質であるといえるでしょう。
最後は「音楽本位」のシンプルな決断を
混沌とした状況の中、たくさんの人がそれぞれの意見を言い、本当にどうすればいいのか、一体何を目指せばいいのか、時には何もかも分からなくなってしまう事もあると思います。
しかし、私たちエンジニアやプロデューサーの究極的な存在理由は、音楽に宿る個性をたった一つ引き出し、最高の形で収録するという、ただそれだけの事です。そして、ただそれだけのことを追求すらできないことがあれば、それは単純にその環境や現場が未熟なのです。
若く可能性に満ちた頭を、無用な事で悩ませたりしないでください。圧倒的な瞬間を引き出す為には手段を選ばず、誰が何と言おうが自分のセンスと技術をひたすら磨き、信じ続ければ良いだけです。
食べ物や衣服と違い、音楽が聴けなくて死ぬ人は居ません。しかし、だからこそ、安物は必要ないのです。
妥協せず、自分の信じる最高の音をぜひとも追い求めて下さいね。
補足:考え方とアプローチの一例
上の三つの具体例に関して、音の方向性などについて事前にアーティスト側とコミュニケーションが取れており、演奏技術も申し分無く、特にアクシデントも起こらないという前提で、私ならどうするか考えてみました。もちろん状況次第で判断は変わりますが、ほんの参考になれば幸いです。
ベースアンプ
ラインも録りますが、十中八九、アンプも同時にマイクで収録します。この段階ですでに最終的な音像に限りなく近くなる様、その場でしっかりと音を決めてしまいます。
ラインの上にマイクで収録した部屋鳴りを含んだアンプを混ぜると、音にライブ感が増し、演奏自体が持つ本来のグルーヴがより強調されます。各パートを別々にオーバーダブして行くタイプのレコーディングの場合、このベースをモニタリングしながら演奏する後発メンバーに良い影響を与える場合も多いです。あとでリアンプするという選択肢は、この時よっぽどマイク録りの結果がどうしようも無い事態に陥った場合以外、私個人としてはあまり考えません。
ギターのエフェクト
ディレイは場合によりますが、半分以上の場合は掛け録りしてしまうと思います。ギタリストの好みのペダルやアウトボードがあるならその音をその場で収録したいし、先ほど述べたように、ディレイのフィードバック音にも部屋鳴りを含ませられるという事もあります。逆に、ディレイ音に部屋鳴りのキャラクターを持たせたくない場合や、ディレイ音をグリッドに完全にシンクさせたいとかいう別の理由があれば、アンプだけを録り、エフェクトはあとから掛ける手法を選択します。
ボーカルコンプ
これについては、私も録りの段階で極端な設定にすることはほぼなく、大体2-3dB未満のコンプレッションで落ち着くことがほとんどです。音楽にもよりますが、基本的にボーカルは楽曲の芯となる存在なので、ダイナミクスは限りなく自然な状態を保つことに注力します。ミックス段階でそれ以上にパンチが必要な場合は、半分以上の場合はダイレクトコンプレッションでなく、パラレルコンプを使います。また、ダイレクトコンプを掛けるにしても、種類の違うコンプを選択すれば潰し方が変わるので、例えば同じ5dBを処理するのでも、単体でやるより、二種類のコンプを使った方が微妙なニュアンスをコントロール出来る場合があります。
ちなみに、レコーディング時に使うコンプは基本的にその場にあるものから選びますが、一般的な話だとおそらく1176やLA2Aか、それに近いキャラクターを持ったものから優先的に選んでいくと思います。







